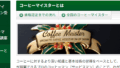最近、美容と健康に関心のある人たちの間で
話題になっている「サジー」。
SNSや雑誌でもよく見かける名前ですが、
どんなものか気になっている人も
いるのではないでしょうか?
目 次
サジーって何が良いの? 豊富な栄養成分がすごい!

サジーには、
100種類以上の栄養成分が含まれているんです。
特に注目したいのは、
ビタミンA、C、Eが豊富なこと。
ビタミンCはレモンの約9倍、
ビタミンAはプルーンの約22倍とも言われています。
これらのビタミンに加えて、
体内で作れない必須アミノ酸や、
ポリフェノール、食物繊維も
入っているからうれしいですよね。
普段の食事で足りない栄養を手軽に補えるので、多くの人が注目しているんです。
サジーを美味しく飲むには? おすすめの飲み方3選

という人もいるかもしれません。
でも大丈夫!飲み方を工夫すれば、
美味しく続けられるんです。
美味しく飲むための活用法をご紹介しますね!
ジュース割り:
りんごジュースやオレンジジュースで割ると、酸味がマイルドになって飲みやすい!フルーティーな味わいで楽しめます。
ヨーグルトにかける:
サジーの酸味とヨーグルトの酸味が相性抜群。朝食やデザートにプラスするのもおすすめです。
サジースカッシュ:
炭酸水で割ってハチミツを少し加えるだけ。さっぱりしたドリンクで気分転換にもなります。
おうちでサジーを育ててみよう! 栽培方法と収穫のコツ

サジーの木は、
乾燥や寒さに強いので、
意外と育てやすいんです。
自宅で栽培に挑戦してみるのも楽しいかもしれません。
栽培する時は、
まず苗を用意しましょう。
サジーは雄と雌の株があるので、
実を収穫するには両方植える必要があります。
日当たりと風通しの良い場所を選んで植え付けます。
水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。
肥料は、植え付け時と年に2回程度でOKです。
収穫時期は、だいたい秋頃。
実が黄色やオレンジ色に熟したら、
枝ごとハサミでカット。
収穫した実は冷凍保存すると長持ちしますよ。
世界中で愛されるスーパーフルーツ「サジー」の歴史
サジーは、アジアやヨーロッパの寒い地域に自生する植物。
実はすごく歴史が古いんです。
昔から栄養価が高いことで知られていて、
食べ物として重宝されてきました。
日本で「サジー」と呼ばれていますが、
世界では色々な名前で呼ばれています。
英語圏では「シーバックソーン(sea buckthorn)」、中国語では「沙棘(シャーチー)」、
フィンランドでは「トゥルニ」。
シーバックソーンは「海の棘のある木」という意味で、
海岸沿いに生えていることが由来みたいです。
中国では、昔のモンゴル帝国の時代から食べられていたという記録も。
世界中で古くから人々の生活を支えてきたスーパーフルーツなんですね。
サジーを飲むって、なんだか瞑想みたい?
禅の修行に
「只管打坐(しかんたざ)」
という言葉があります。
これは、何かを求めたり、
結果を期待したりしないで、
ただひたすら座禅をすること。
サジーを飲む行為は、
この「只管打坐」の考え方に近い気がするんです。
飲むことに集中する:
サジーの酸味って、飲んでいる時に「今、口の中にある!」って意識させてくれますよね。
他のことを考えずに、ただ「必要なものを取り入れている」という行為に集中できるのが、なにげに禅っぽい。
結果にこだわらない:
サジーを飲む人は、サプリみたいに「これを飲めば〇〇に良い!」
って期待するだけじゃなくて、
毎日「良いものを摂っている」
っていう積み重ねを大事にするんじゃないかな。
すぐに結果が出なくても、
「飲むこと」自体に価値を見出すのは、
禅の「手放す」精神に通じるのかも。
健康や美容について色々悩むよりも、
サジーを飲むことで、自然の恵みを感じて、
自分の心と体を大切にする。
サジーを飲むことは、
自分自身と向き合う静かな時間なのかもしれません。
つまり、サジーを飲む人は、
日々の生活の中で心と体のバランスを整えようとしているのかも。
サジーは、
自分と向き合うための「道具」なのかもしれませんね。